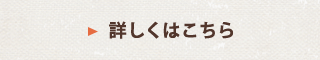リードの引っ張りは「リーダー願望の現れ」ではない
お散歩で犬がリードを引っ張るのは、前方に興味の惹かれるものがあったり、引っ張った結果そこにたどり着けたという経験による学習があったり、その他にリードが後ろに張ることで体が前方に動くという行動的性質や犬種特性など、様々な要因が考えられるのですが「リーダー願望の現れ」ではありません。
— コンピス (@kompismedhund) July 12, 2025
先日このようなポストを行いました。
この投稿について少し深堀していきます。
■犬が飼い主より前を歩くのはリーダー願望?
散歩中、犬が飼い主より前を歩く姿をよく見かけますよね。リードをグイグイと引っ張って歩く犬もいます。
この行動は「リーダー願望の現れ」と言われてきました。
犬は群れで生活する動物であり、群れが移動する際に先頭を歩くのは主導権を握るリーダーだと考えられてきたからです。
この考え方は、犬の祖先であるオオカミの群れ行動から考えられます。
群れではリーダーが先頭に立ち、進行方向を決めるのが一般的とされていました。
そのため、犬が前を歩くと「自分がリーダーだ」と示している、と解釈されているのですね。
こうした背景から、犬の訓練方法の一つとして「リーダーウォーク」というものがあります。
これは、犬を飼い主の横につけて歩かせ、アイコンタクトや指示に従わせることで飼い主のリーダーシップを示すことができると考えられています。
このリーダーウォークという訓練方法は、長い間とても重視されてきました。
下位の犬は上位の犬に対して困った行動はせず何でも従う存在だと考えられています。
そしてこの方法によって飼い主は愛犬に対して優位性を示すことができるわけです。素晴らしいですよね。
実際、犬のさまざまな問題行動に対して、このリーダーウォークは積極的に取り入れられています。
例えば、飼い主に噛みつく犬や、室内で「静かに!」と言っても言うことを聞かず吠え続ける犬に対しても、リーダーウォークが実施されています。
■犬が前を歩くのはリーダー願望ではない?
上記に書いた通りこれまで散歩中に犬が飼い主より前を歩くと「リーダーになりたがっている」と言われてきました。
しかし現代の動物行動学ではこの考え方は支持されていません。
根拠となり得るものを探してみると、イエローストーン国立公園で行われたオオカミの群れにおけるリーダーシップ行動を示した研究があるようです。
Leadership behavior in relation to dominance and reproductive status in gray wolves, Canis lupus
この研究では上位の繁殖した個体が移動中に先頭を歩く割合が高いと報告されています。
しかし、これは「常に固定のリーダーが先頭を歩く」ということを意味しているのではありません。
群れが大きい場合は、先頭を歩く個体は状況により変わり、狩りや移動の目的、地形によって柔軟にポジションが入れ替わることもあったようです。
さらにスウェーデンの動物行動学者Lars Fältは自身の著書『Hundens språk och flockliv』でオオカミの群れにおけるスペシャリストという概念を述べています。
群れ内ではリーダーがすべてを仕切るのではなく、特定の能力を持つ個体が状況に応じてイニシアチブを取ることが観察されています。
たとえば、警戒心が強い個体が偵察に立ち、移動ルートや食事場所などの地形に詳しい個体が群れの移動をリードする。
つまり、「先頭を歩く=群れのリーダー」という考え方自体が誤りなのですね。
■あえて口に出して否定する理由
「リーダー願望ではありません」と私はよく口にします。しつこいくらいです。
なぜなら、いわゆる「リーダー論」や「上下関係」という考え方は、ドッグトレーニングにおいて大きな障害になるからです。
よく言われる「オオカミの群れでは上位の個体が先頭を歩き、他が従う」という話。
これは単に弱い個体が強い個体に従っているのではありません。
その個体がスペシャリストとしての働きよって群れに利益をもたらすからです。
目的地に到着できる、
食事場に行ける、
安全に移動できる。
だから群れはその個体に従うのです。
分かりますか?
「群れを追従させることで優位性が築かれる」
のではなく、
「群れに利益がもたらされるから優位性が保たれている」
ということです。
ここで冒頭で触れた「リーダーウォーク」という訓練方法に話を戻します。
これは「犬を追従させることで飼い主のリーダーシップを示せる」という考え方に基づいています。
この理屈がいかに的外れか、もうお分かりでしょう。
形だけまねても意味がないということです。
愛犬が飼い主に噛みつくことを、飼い主が頼りないからだと考えて、お散歩でリーダーウォークが実施される。
室内で「静かに!」と言っても全く聞かず吠え続ける犬に対して、リーダーの言うことに従うように、お散歩でリーダーウォークが実施される。
果たしてその取り組みに効果は期待できるでしょうか。
※これはリーダーウォークという方法自体を否定しているのではありません。何を目的に行われるかという話です。
犬との関係性についてリーダー論や上下関係という考え方は一般に広く浸透しています。
そしてそれを広げたのは、私たちドッグトレーナーです。
だからこそ、それをきちんと否定することもドッグトレーナーの役割だと私は考えています。
■それでは犬はどこを歩けばいいのでしょう?
今回のテーマに話を戻します。
これまで「犬は飼い主より前を歩かせてはいけない。自分がエライと勘違いさせるから」と言われてきました。
しかしその考えは誤りだということが分かりました。
では、
お散歩の際、犬はどこを歩けばいいのでしょう。
結論から言うと、どこを歩いてもかまいません。
飼い主の前でも後ろでも、右でも左でもどこでも構わないと私は考えています。
ただし、それは問題が生じていないということが前提ですね。
たとえば、犬がリードを強く引っ張って苦しそうなら、引っ張らずに歩く練習をするのもいいでしょう。
また、車道側を歩いて危ない場合は、内側を歩くように促すのもいいですね。
私はフレキシブルリードをお勧めしません。
ノーリードも否定します。
飼い主にも犬にも周囲にも危険が及ばないなら、犬はどこを歩いてもいいでしょう。
それによって飼い主と愛犬との関係性が壊れてしまうことはありません。
上下関係が逆転するなんてこともありません。
もしも散歩中に問題が生じるなら、それぞれに対してその都度に対応策を考え進めていきます。
そういった取り組み一つ一つの繰り返しが、愛犬との楽しいお散歩につながっていくのですね。
今回は、「リードの引っ張りはリーダー願望の現れではない」ということについて深堀しました。
他の内容についても少し詳しく書いていきたいと考えています。
更新はゆっくりになるかもしれませんが、よろしくお願いします。