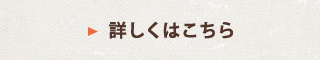行動の働きを考えよう。他の犬に吠える愛犬を叱るとどうなるか。
危険を避けるという反応は、動物が生きるために備わっている基本的な行動です。
主に痛みを感じる刺激や、過剰なほどの大きな音、強い刺激臭といったものに見られる行動です。
危険を避ける働きを持つこの行動は、生存のためにおこなわれるため、その行動に対する欲求はとても強くなります。
これに属する問題行動が、短時間でいとも簡単に激しく悪化していくのは、その行動に生存を目的とする高い動機づけがあるからではないでしょうか。
今回は、この「危険を避ける行動」について書いていきます。
この危険を避ける行動は「回避行動」または「逃避行動」と呼ばれます。
心理学(行動分析学)によると、
回避とは、これから生じる嫌悪刺激を事前に避ける状況
逃避とは、現前の嫌悪刺激を避ける状況
とされています。
(参照:行動分析学辞典)
例えば、
爪切りを持って近づく飼い主から逃げるという、愛犬のその逃げる行動は「回避行動」でしょう。
これから生じる爪切りという嫌悪刺激を事前に避けるために逃げるのですね。
爪切りをされている最中に暴れる行動は、逃避行動ですね。
今起こっている爪切りという嫌悪刺激を避けるために、もがき暴れます。
散歩中に他の犬を見ると吠えるという行動も回避行動の場合があります。
幼い頃に他の犬と接触を持てなかった事や、他の犬から受けた不快な経験から、他犬を嫌う犬は多いです。
他の犬を見た時に相手を追い払おうとして吠えるその行動は、不快な相手を回避する働きを持つ「回避行動」と言えます。
この回避行動に属する愛犬の問題行動を叱ってやめさせた場合、どうなるのでしょうか。
答えは簡単です。
同じ働きを持つ別の回避行動を行うようになります。
「回避行動をやめさせても別の回避行動が出るだけ」
ということです。
例えば、
散歩中に他の犬に吠えることを叱ってやめさせた場合、どうなるでしょうか。
もちろん愛犬は別の行動で相手を避けようとするようになります。
吠えて相手を回避できないのなら、逃げようとするかもしれません。
でも犬たちはリードにつながれているため、逃げることはできません。
逃げることができなければ、噛みついて相手を遠ざけよう(回避)とするでしょう。
このような事を繰り返していると、愛犬はどんどん攻撃的になり、事態は深刻になっていきます。
逃避行動に関しても同じことが言えます。
このような事態を防ぐために、問題行動には慎重に対応しなければいけません。
トレーニングの方向性として、
好ましい方法で回避する術を教えるのもいいかもしれません。
本人が回避行動を示す必要性を感じないくらいの状況を作るのもいいですね。
相手に対して抱く不快感を取り除けるようなトレーニングもあるかもしれません。
まずはそういった方法を試してみませんか?
愛犬の問題行動を叱ってやめさせたとしても、それで終わるとは限りません。
別の問題行動が出現する可能性があります。
多くの場合、そこで事態は深刻になります。
この記事の冒頭で書いた通り、回避行動や逃避行動には、生存を目的とする高い動機づけがあります。
接し方を間違っていると、あっという間にその問題行動は悪化していくかもしれませんよ。
↓↓ブログランキングに参加しております。クリックしていただければ励みになります。

ドッグトレーナー・訓練士ランキング
![]()
にほんブログ村