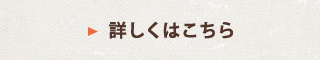犬の問題行動の原因を考える。原因と思っているそれは本当に原因ですか?
仕事場での出来事として想像してみてください。
あなたの同僚はよく遅刻をします。よく仕事でミスもします。
教育係である上司はどうするでしょうか。
もしかしたら、遅刻をするのはだらしない性格だからと考えて、その性格を正そうと叱りつけるかもしれません。
仕事に対する意識の低さからミスが起こると考え、飲みの席で部下に仕事のやりがいを語るかもしれません。
このような事は昔からどの会社でもよく見られる伝統的なものだと思いますが、はたしてどれだけの改善が見られるでしょうか。
改善されたりされなかったり、されたとしても一時的だったり、、ではないでしょうか。できればもっと具体的な改善策を考えたいですね。
心理学(行動分析学)は、行動的問題の原因を、性格や意識といった個人の内面から考えることを避けます。
「だらしのない性格だから・・・」や「意識が低いから・・・」といった表現は、行動の原因を説明しているように見えますが、問題となっている行動を別の言葉で表現しているだけだからです。
だらしない性格だから遅刻をする、と考えると、以下のようになってしまいます。
彼はなぜ遅刻をするの?
彼はだらしない性格だからです。
どうしてだらしない性格だと分かるの?
遅刻をするからです。
このように行動と原因が循環してしまっていることを「循環論の罠」といいます。
行動の原因と考えているものが、原因でないのなら、それに対する試みに効果はあるでしょうか。
また、だらしない性格や意識が低いといった、個人の内面を責めるだけで具体的な解決策に繋がらないことを「個人攻撃の罠」とも言われます。
このような状態に陥らずに適切な解決策を見つけるために、行動分析学は行動の原因を、個人の内面ではなくあえて環境側に考えます。
部下もわざとミスをしているわけではありませんよね。
部下がミスをする時、その人がミスをしてしまう環境(状況)がそこにあるという事です。その環境を変えないかぎりミスは続いてしまうでしょう。
遅刻をするのは、もしかしたら前日の夜に夜更かしをする環境があるのかもしれませんし、朝に家を出るのが遅くなる環境があるのかもしれません。その環境を変えないとなかなか改善は難しいでしょう。
もしも部下がわざとミスをしていたとしても(ありえないことですが)、行動分析学はその原因さえも環境側にあると考えます。少し変わった考え方かもしれません。その部下が悪意を持っていようがいまいが、その行動の出現に大きな影響を与えている要因は環境にあると考えるのですね。
このように行動は環境に制御されているという考え方が行動分析学の特徴です。
わざとミスをしたその部下を処分するべきかどうかはまた別の話です。
以前、ツイッターで臨床心理士の先生がつぶやいた「痴漢で一番悪いのは満員電車ですよ。状況が人の行動を決めるんです。」というツイートが話題になっていました。
「一番悪い」という表現から多くの誤解を招いていたこのツイートですが、人が密着する状況で痴漢行為が多いことや、空いている車内での痴漢行為は明らかに少ないことは容易に想像できますよね。
ハロウィンや日本代表サッカーなどのイベント時に、渋谷のスクランブル交差点に人が集まる中で痴漢行為が続出していますが、普段のスクランブル交差点ではそのような行為は格段に少ないのではないでしょうか。
実際に痴漢行為の出現に影響を与えている要因として、大勢の人が密着しているという環境は大きいと思います。
この話題つながりで、ショートエクステを付けると痴漢されなくなったという報告も目にしました。
奇抜な色を使うことで防御効果があるそうです。
ショートエクステが視界に入るという環境が痴漢行為の出現を減らしています。
行動の生起頻度が変わる要因として、環境が影響しているのは明らかですね。
ただなんだかんだ言っても、
痴漢は犯罪です。
そろそろドッグトレーニングの話に入りたいと思います。
私がこの行動分析学の考え方を何度も紹介するのは、これまで行われてきた、そして現在も行われているドッグトレーニングが、まさに冒頭で紹介した「循環論の罠」に陥ってしまっているからです。
その結果、多くのドッグトレーナーが、犬は醜悪な生き物であるかのように考えてしまっています。
犬は常にリーダーの座を狙っている存在で、飼い主が頼りないと途端に挑戦者としての牙を見せる支配的な生き物だと。
特に飼い主の指示を無視するような“不服従な行動”や、唸ったり噛みついたりするような攻撃的な行動は、飼い主への挑戦として考えられ、厳しく罰せられてきました。(個人攻撃の罠)
犬が飼い主を支配しようと振舞うのですから、そのような悪行は罰せられて当然と人間が考えるのは自然な事でしょう。
そのような傾向を表してか、昔のドッグトレーニングマニュアルには、犬たちの激しい問題行動に対して「犯罪」という言葉が使われています。
「噛みつくのは支配的な習性があるからだ。」
「指示を無視するのは挑戦的な意識があるからだ。」
このような考え方から、犬の地位を下げる方法がこれまでにたくさん編み出されてきました。
いくつか例を挙げます。
「飼い主が犬よりも先にごはんを食べなければいけない。」
「犬をソファやベッドに乗せてはいけない。」
「引っ張りっこ遊びをしてはいけない。」
愛犬の噛みつく行動に対して、または愛犬が指示を無視することに対して、これらの方法にどれだけの効果が見られるでしょうか。
私は難しいと思います。
冒頭で紹介した「遅刻をするのはだらしのない性格だからだ。」「ミスをするのは仕事に対する意識が低いからだ」とまったく同じ考え方ですよね。
行動分析学を学んでいるドッグトレーナーなら、犬が指示に従わないのはその行動への強化が不十分なだけ(練習不足)ということや、噛みつく行動には不快刺激を避けるという回避や逃避の可能性があることも簡単に想像できるでしょう。
行動の原因を安易に内面から考えようとすることで、問題解決を遠ざけてしまっている典型的な例ですね。
人は循環論の罠や個人攻撃の罠に簡単に陥ってしまうと行動分析学は指摘しています。
私も、自分自身に対して思い当たるふしがたくさんあります。
問題となっている行動の原因はどこにあるのかしっかりと見極めていきたいです。
↓↓ブログランキングに参加しております。クリックしていただければ励みになります。

ドッグトレーナー・訓練士ランキング
![]()
にほんブログ村