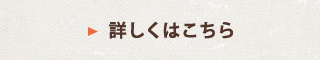愛犬がごはんを食べない・・・その要因を考える
「いつも喜んでごはんを食べてくれているのに急に食べなくなってきた。」
「動物病院で愛犬が痩せていると言われ、体重を増やしたいがごはんを食べてくれない」
「人間の食べ物ばかり欲しがって自分のごはんを食べない」
このように愛犬のごはんに関するお悩みっていろいろとあると思います。
特に「ごはんを食べない」ということについて頭を抱えている飼い主さんは多いのではないでしょうか。
まず最初にお伝えしておきたいことは、「ごはんを食べなくなる状態」はさまざまな病気の初期症状として現れます。
愛犬がごはんを食べなくなったら、まずは獣医師に相談することが大切です。
病気であることを否定してからそれ以外の可能性を考えましょう。
それでは愛犬がごはんを食べないことについてどのような要因があるか考えてみます。
ここでは「食べる」という行為を一つの行動として捉えて進めていきます。
●食べる行動に弱化が起こっている可能性
食行動が減少していることについて、まず思い浮かべるのは行動に弱化が起こっている状態です。
弱化とは「行動した結果、嫌悪刺激が出現したことで、将来のその行動の生起頻度が減少する」という現象です。食べたら不快な事が起こったから食べなくなるということですね。
これにはどのような可能性が考えられるでしょうか。
例えば、口腔内に問題があり、食べた結果痛みが生じたという状態です。
具体的な要因として、重度の歯周病、口腔内損傷、歯の生え変わりなどがあげられます。
蓄積した歯石の影響から歯周病になり痛みが生じている場合は、動物病院で適切な歯科処置が必要になります。そうならないために日頃からのデンタルケアや麻酔下での歯石除去を駆使して歯周病になることを防ぎましょう。
硬いオモチャを齧らせていると犬の歯が割れることがあります。血管や神経が露出するくらい大きく歯が欠けると、そこから細菌が入り炎症や膿瘍が生じて痛みが伴います。こちらも動物病院で適切な歯科処置が必要になるケースです。オモチャ選びは慎重に行いましょう。
ご自宅に木のオモチャはありませんか?犬は木製のオモチャをかじることが大好きです。しかしかじって削れた木の鋭利部分で口腔内を傷つけてしまう事もあります。もしもご自宅にある木のオモチャに、削れて尖った箇所があるなら、ヤスリなどで削っておくといいですね。
歯の生え変わり時期の乳歯は、根がもろく不安定です。硬いドライフードを噛むと痛みが生じる場合もあり、それによって食行動に弱化が起こっている可能性もあります。もしも子犬がごはんを食べない場合は、ドライフードをしっかりとふやかしてあげるか、噛む必要が無いくらいの小さな粒のフードを与えてみてください。
その他の可能性として、体調を崩した犬がドライフードのニオイを嗅ぐことで吐き気をもよおし、その吐き気が嫌悪刺激となることもあります。食行動につながるニオイを嗅ぐ行動が弱化されるため、食行動も同時に低減します。
●食べる行動への動機が下がっている可能性
次は食行動の動機づけが低下し行動が抑制されている状態について考えます。
この動機づけについては、行動分析学の「動因操作」という考え方を参考にします。
弱化は食べた後何が起こったかという所に注目しているのに対して、この動因操作は食べる前の出来事に注目したもので、生物学的要因、環境的要因、社会的要因という3つの側面から焦点があてられることが多いようです。
犬に関しては生物学的要因と環境的要因が重要になるのではないでしょうか。
動因操作には2つの機能があります。(参照:はじめてまなぶ行動療法)
1つ目は強化子(ごほうび)や弱化子(嫌悪刺激)の有効性を強めたり弱めたりする機能(価値変更効果)です。これは先に取り上げた弱化に大きく関わる機能ですね。
2つ目はその強化子や弱化子に関連する行動を引き出したり抑制したりする機能(行動変更効果)です。
ここでは2つ目の行動変更効果が働いて食行動が抑制されている状態を考えていきます。
●生物学的要因
食行動の動機づけが低下する生物学的要因としてまず思い浮かべるのは、犬が満腹の状態です。でもこれは当たり前の事なので横に置いておきます。
その他で考えられることは、胃腸炎、腎不全、感染症といった食欲低下を症状に持つ病気です。
冒頭でも紹介した通り、食欲低下はさまざまな病気の初期症状として現れます。治療を必要としている状態なので動物病院に連れて行きましょう。
また服用している薬の副作用として食欲低下が起こり、食行動が抑制されている可能性もあります。獣医師に相談してみましょう。
食物に対する飽きも、食行動の動機づけが低下する要因として考えられるのではないでしょうか。
食物への飽きは、馴化という現象によって説明されています。
馴化とは、刺激の繰り返しによりその刺激に対する反応が弱まる現象です。
香りや味、食感などの食物刺激に対して馴化が進むことで、その食べ物が食べるための反応を引き起こす効果が弱くなっていくと推測されます。
馴化の特徴として、提示される刺激に変動性を持たせると馴化の進行が遅くなるというものがあります。
香り、味、食感などに変化を持たせることで、食べ飽きることを防げるかもしれませんね。
●環境的要因
食行動の動機づけが低下することについて、環境的要因にはどのような事が考えられるでしょうか。
例えば、
新しい家に引き取られて間もない犬はごはんを食べないことがあります。慣れていない場所で緊張しているのかもしれません。
いつも愛犬が喜んで食べているジャーキーなのに、動物病院の診察台の上では食べないということもよくありますよね。
外を怖がる犬は、散歩中にフードをあげても食べないでしょう。
これらは環境によって食行動の動機づけが低められ行動が抑制されていると言えます。
私はトレーニングのご褒美としてフードを用いる場合、必ずその場所でそのフードを食べるかどうかを確認します。
環境的要因によって食べられないという事があるからです。
そしてもしもその犬がフードを食べられない場合、その要因が環境にあると考えられる時は、まずその場所でフードを食べられるようになることを目標に立てます。
犬がごはんを食べないという事についていろいろと考えてみました。
今回取り上げたもの以外にも、食行動が低減する要因はたくさんあると思います。
基本的に犬たちの食べ物は彼らが食べるように作られているため、多くの犬にとっては問題ないでしょう。
ただ、やはり食に対する性質はそれぞれ犬によって違うため、合わない犬もいるんですよね。
このような場合は犬が食べる物を与えることが多いため、食事内容にどんどん偏りが出てくることがあります。
この偏食についてはまた別の記事で取り上げたいと思います。
愛犬のごはんについて悩まれている方の参考になれば幸いです。
コンピスでは月に1回無料セミナーを開催しております。ご興味のある方は是非お越しください。→詳細はこちら
↓↓ブログランキングに参加しております。クリックしていただければ励みになります。

ドッグトレーナー・訓練士ランキング
![]()
にほんブログ村