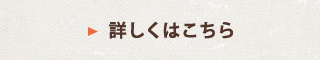犬同士の会話。飼い主が介入するべきタイミング。
ブログやフェイスブック、ツイッターなど、インターネット上には動物たちのかわいい写真や動画があふれています。
私もそんな動物たちの愛らしい様子に癒されているのですが、中にはヒヤヒヤしてしまうようなものもあります。
例えば、犬同士の喧嘩に繋がるかもしれないものや、飼い主が噛みつかれてしまうかもしれないようなものです。
先日も、犬同士のおもしろいやり取りとして、ある動画が紹介されていました。
それは、2頭の犬がソファの上でお互いにくっついて座っている場面でした。
1頭の犬はお尻にふれられることが苦手らしく、くっついて座っているもう1頭の犬に対して歯を見せて唸っていました。
しかし、唸られているそのもう1頭の犬は、我関せずという感じでのんびりと座っています。
その様子を、「怒られているのに気づいていないのんびり屋さんの犬」というような形で紹介されていました。
私は、このような場面を目にしたら、すぐに介入するべきだと考えています。
多頭飼いで大きな問題となるのは、犬同士の仲です。
仲が悪く激しい喧嘩をするので一緒にさせられない、という多頭飼いでの問題は実際によくあります。
毎回大ゲンカで、どちらかが(または両方が)大きな怪我を負ってしまい、その喧嘩を止めようとした飼い主さんも激しく噛みつかれて大怪我を負ってしまうようなものです。
2頭を完全に隔離して飼育しなければいけないような、そのような状況に陥ってしまっているご家庭はとても大変です。
基本的に、犬同士が激しく喧嘩をすればするほど、その犬たちの仲は悪くなっていきます。
終いには、一緒に過ごせなくなるくらい仲が悪くなってしまいます。
そうならないために、飼い主は犬同士の喧嘩が起こりやすい状況をきちんと管理したり、介入するべきタイミングを把握したりしておくといいでしょう。
例えば、冒頭で紹介したソファに座る2頭の犬のケースです。
1頭の犬がお尻に触れられて唸っているのに、相手の犬は全く気にしていません。
相手に離れてほしくて唸っているのに、相手が離れてくれない時、その唸るという行動はどのように変化するか考えてみましょう。
通常、唸っても相手が離れてくれなければ、唸っても意味が無いので、唸らなくなっていきます。
行動しても目的が達成されない時その行動が減少するということを消去と言います。
そしてこの消去が起こる時、一緒に消去バーストと呼ばれる現象も起こることが行動研究によって明らかになっています。
消去バースト:消去手続きを開始した直後、一時的に行動の頻度や強度が爆発的に増えること
(行動分析学入門より)
「行動してもうまくいかないから、もっと頑張ってやってみよう」というようなイメージかもしれませんね。
この消去バーストがどれくらいの激しさで出現するかは、その時の状況によって変わります。
また、この消去バーストは行動の頻度や強度が増えるだけではなく、行動の種類に広がりを見せる特徴もあります。(メリットの法則p73)
お尻に触れられている時、唸っても相手が離れてくれないなら、もっと激しく唸るかもしれません。唸ってダメならその犬はどうするでしょうか。
多くの場合、この段階で噛みつく行動が出現します。
そして犬たちは大ゲンカです。
このような事を繰り返すことで、犬同士の仲はどんどん悪くなっていくのですね。
ご紹介したケースのように、犬同士の会話が成立しておらず、行き違いが起こる可能性がある場合は、飼い主が介入するべきだと考えています。
今回の場合は、唸られてもその犬がその場を離れないのであれば、その唸られている犬の名前を呼んで、その場から離れるように指示してもいいでしょう。
(※ここで唸っている犬を叱るのは危険です。犬の唸る行動に対して威圧的に接すると、防御性攻撃行動を引き出してしまいもっと攻撃的になる恐れがあります。また叱ることで唸る行動をやめさせると、次からその犬は唸らずにダイレクトに噛みつくようになる可能性もあります。)
もちろん、このような介入をしなくても何事も起こらないかもしれません。
もしかしたら、唸っても相手がどいてくれなければ、そのまま2頭で一緒に寝るかもしれません。
それなら介入する必要なんてないかもしれません。
でもそれは実際に試してみないと分からないことです。
そしてそうならなかった時のリスクがあまりにも大きいので、私は予防という形で介入することをお勧めしています。
犬同士の仲が悪い、お互いに血を見るケンカをする、一緒に過ごすことができない、
こういった多頭飼いの行動的問題は、このような些細な行き違いから始まります。
↓↓ブログランキングに参加しております。クリックしていただければ励みになります。

ドッグトレーナー・訓練士ランキング
![]()
にほんブログ村