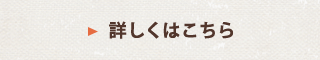愛犬との暮らしに上下関係(主従関係)は必要ありません
これまで40年以上もの長い間、ドッグトレーニングの世界では「上下関係」や「主従関係」という考え方が使われてきました。
この考え方は飼い主が「リーダー」であり犬は「従うべき存在」という前提に基づいています。
多くのトレーニング方法もこの上下関係を重要視して犬たちに「服従」を求めるものでした。
その結果、犬の問題行動を重篤化させてしまう方法や、虐待と呼べるほどの激しい体罰、また効果のない方法が延々と繰り返されるというような誤った方法が編み出されてきました。
近年では多くの団体から「上下関係に基づくトレーニング方法は科学的根拠が乏しく、犬に恐怖や不安を増加させる可能性がある。」といった声明やガイドラインが出されています。
しかしこのような情報や考え方は、まだまだ一般の飼い主やペット業界の現場に十分に浸透しているとは言えません。
実際にトレーナーや獣医師、ペットショップのスタッフなどの間でも「上下関係をしっかり作らなければならない」「飼い主を下に見ているから犬が言うことを聞かない」という考え方が根強く残っている印象を受けます。
この上下関係、主従関係という考え方をここまで広く社会に浸透させたのはドッグトレーナーです。
だからそれをきちんと否定するのもドッグトレーナーの役割だと考えています。
以上のことを踏まえて今回は「上下関係」について改めて詳しく書いていきます。
今回の内容は私がこれまで学んできたものをまとめたものであり私見も含まれます。
愛犬と幸せに暮らすための考え方のひとつとして読んでいただければ幸いです。
●上下関係は必要?
愛犬との暮らしにおいて「上下関係」や「主従関係」といった関係性が適切でないことが、なかなか広く理解されない要因の一つに表現の仕方に問題があると私は考えています。
一般的に「上下関係」という言葉を聞くと、学校や会社での「上司と部下」「先輩と後輩」「先生と生徒」といったイメージを持つ方が多いと思います。
とても身近に感じますよね。
馴染みもある分、必要なものだとも認識する人も多いと思います。
ドッグトレーニングの分野において「上下関係」と日本語で表現されているこの考え方は、英語では「支配性理論(dominance theory)」と呼ばれています。
支配・・・何やら不穏な響きですね。
これまで多くのドッグトレーナーが一般に受け入れられやすい「上下関係」という日本語を使って犬の行動を説明してきたことで、言葉のイメージが先行し本来の意味が正しく伝わりにくくなっているのだと私は考えています。
まずはここから整理していきたいます。
●上下関係はどこからきたのか?
そもそも上下関係(主従関係)という考え方はどこから来たのでしょう。
この上下関係の考えは動物の集団内で見られる「直線的な順位制」に由来しています。
1920年代、ノルウェーの動物学者トルライフ・シェルデラップ=エッベ(Thorleif Schjelderup-Ebbe)が行った研究がよく知られています。
彼の「つつき順位」と呼ばれる研究では、ニワトリが資源(餌や寝床)をめぐって争う中で形成される順位制について明らかにされました。
研究のために集められたニワトリたちは囲いの中で集団を作り、資源をめぐってあちこちで争いを始めました。その様子を観察することで、ニワトリたちの攻撃行動の方向性に法則があることが分かりました。
分かりやすく説明するとこのような感じになります。
・個体Aは個体B、C、D、Eをつついて攻撃します。
・個体Bは自分を攻撃した個体A以外のC、D、Eを攻撃します。
・個体Cは自分を攻撃した個体AとB以外のD、Eを攻撃します。
・最後の個体Eは全ての個体から攻撃を受けました。
しばらくの争いの後、ニワトリの間に関係性がきずかれるとともに次第に争いは起こらなくなったようです。
体が大きく力の強い個体が資源を優先的に得ます。争いに負けた個体はそれに従い衝突を避けるようになったということですね。
体が大きく力の強い個体が上位となり、戦いに勝てない弱い個体は下位となる。
このようにしてこの集団の中に直線的な順位制が築かれました。
この「つつき順位」の研究は、その後に他の動物にも適用されました。
興味深いのは、その結果として他の動物にも類似の順位制が確認されたということです。
ニワトリだけではなく、オオカミやサル、草食動物などにも同じような直線的な順位制が観察されました。
そして当時の動物学者たちは、これが群れのシステムだと解釈したのですね。
この現象は現在でも観察することができます。
動物園の猿山で暮らしているサルたちを見ると分かりやすいですね。テレビの動物番組でもボス猿を筆頭に厳しい順位制がよく紹介されています。
酪農業を営む人のSNSの投稿から、ウシが上下関係を築いていることが観察されています。
少し調べると乗馬の世界でもウマに上下関係があるという情報がたくさん見つかります。
そしてオオカミにも厳しい上下関係があると言われています。
それに関連して犬たちにも上下関係があると言われているのは、皆さんご存じですよね。
種が違うのにみんな上下関係。
これって不思議だと思いませんか?
群れのシステムってそんなに単純なのでしょうか。
●つつき順位の問題点
「つつき順位」のように「人為的な閉じられた空間」で観察された行動を、自然の群れで見られるものと同じと考えるのは適切ではないという意見があります。
動物は他の個体と争いになった時、主に3つの選択肢があります。
1つは闘争、その場にとどまって相手に立ち向かう方法です。
2つ目は逃走、相手から攻撃されないようにその場から離れる行動です。多くの場合、戦いに負けた個体は逃走を選びます。
3つ目は従属、負けたあと逃げられない状況だとそれ以上攻撃されないように相手に従います。資源を譲り、顔を背けて体を小さくし、敵意がないことを示すのですね。それがその環境で生き延びるための唯一の方法となるわけです。
つつき順位のような直線的な順位制について考える時、2つ目の「逃走」についてしっかりと考えなければいけません。
つつき順位のニワトリたちは、人為的な閉じられた空間の中にいたため戦いに負けても逃げることができませんでした。
もしもその飼育設備に穴があってニワトリたちが自由に外に出られる環境だったらどうなっていたでしょうか。
彼らはその場にとどまって直線的な順位を築いたでしょうか。
この疑問が、この直線的順位制を考えるためにとても重要になります。
本来、攻撃行動は相手と距離を取るために使われます。
自由に逃げられる環境なら、戦いに負けたニワトリはその場から逃げて行ってしまうでしょう。
つまり直線的な順位をつくるためには、その場から逃げられない環境が必要だということです。
戦っても勝てず、逃げることもできず、唯一残された手段は言うことに従うだけというのは、とても支配的な関係性と言えるでしょう。
自然で暮らしている群れの中で、もしもお互いが攻撃的に争っていては群れが崩壊してしまいます。
近年の動物行動学の研究では、群れについて「社会的絆や協力を基盤にした複雑な社会構造を持つ集団」というような説明がされています。
単純な上下関係や順位制に支配されているようなものではないということですね。
●上下関係の正体
私たちの身近にいる犬たちは「閉じられた空間」で生活していると言えます。
彼らを閉じ込めている囲いは、リードに繋がれている状況や、飼い主と同じ部屋にいる状況などになるでしょう
もしもそこで飼い主が愛犬に暴力的にふるまえば、直線的な順位制が築けてしまうのですね。
体が大きく力の強い個体が上位になり、戦いに負けた弱い個体は従うようになりますから。
これが上下関係の正体です。
長年ドッグトレーニングが掲げてきたもの、現在多くの団体が反対を表明しているもの、私が強く批判しているもの、それがこの上下関係です。
皆さんがイメージされていたものとは大きく異なるのではないでしょうか。
●上下関係を築くことの危険性
愛犬と上下関係(直線的な順位制)を作るには愛犬と戦うことになります。そして、勝つ必要があります。
しかしここに大きな問題があります。
誰もが必ず愛犬に勝てるとは限らないということです。
上下関係を築こうと挑むと、その後はことあるごとに力比べの争いが続くことになります。
飼い主は自分の力を示すために体罰を使うようになり、その体罰も次第にエスカレートしていきます。
犬の攻撃行動も争いを繰り返すごとにどんどん激しくなります。
そして大きな事故が起こるのはまさにこの時です。
愛犬が大きな怪我をすることもあれば、飼い主自身が大きな怪我を負うこともあります。
このように悲惨な結果を招いてしまうのですね。
もし仮に愛犬との戦いに勝ち従わせることができたとしても、それはあくまであなたに対して従属しただけだということを理解してください。
思い出してください。つつき順位のニワトリたちの行動を。
個体Aはすべての個体を攻撃し、個体Bは自分を攻撃したA以外の個体C、D、Eを攻撃していました。
つまり、個体Aに従属した個体Bは、A以外の他の個体に対して連鎖的に攻撃をおこなっていました。
あなたに従属した犬も、他の家族に対して同じように攻撃行動を示すかもしれません。
その攻撃の対象は、あなたの小さなお子さんかもしれませんよ。
上下関係を築こうとすることが、どれほど危険か理解してもらえるのではないでしょうか。
●上下関係という詭弁
犬の行動は上下関係という言葉で簡単にこじつけられてしまいます。
犬は自分の言葉でそれを否定できませんからね。
犬が吠える時、噛みつく時、言うことに従わない時、「上下関係が逆転していますね」というのは古いドッグトレーニングの常套句です。
犬の行動を安易に上下関係にこじつけてきた結果、様々な問題が生じています。
例えば、
・効果のない方法が提案されます
望ましくない犬の行動の原因を安易に上下関係の逆転にあると決めつけ、目の前の問題よりも自分たちが想像した原因を正そうと取り組みが行われます。
その結果効果のない方法が延々と繰り返されます。
例えば飼い主に噛みつく行動の原因を上下関係の逆転にあるとされ、オオカミの群れが移動する際はリーダーが先頭を歩くということから(←そもそも間違い)、飼い主の後ろを歩かせる方法が提案されます。
行動的に考えると噛みつく行動と飼い主の後ろを歩く行動に直接的な関係がないことが分かります。
・問題を悪化させます
上下関係は厳しく教えるものというイメージから体罰や叱責が積極的に行われます。
それが犬の防衛的な攻撃行動を引き出してしまい飼い主との関係は悪化します。
その悪化は飼い主の体罰をさらにエスカレートさせ、その結果飼い主と犬双方が大きな怪我をする事に繋がります。
・犬を悪者にします
ボスの座を狙っている、飼い主を見下している、バカにしているというように、あたかも犬が醜悪な生き物であるかのような印象を与え、そのような犬たちは罰せられて当然として体罰が行われてしまいます。
愛犬の行動に困り果てている飼い主は、その困った行動に対して強く被害的にとらえていることが多いです。
そこで犬を悪者にするような説明を受けたらどうなるでしょうか。
仕返しとばかりに体罰や非倫理的な対応が行われたり、かわいく思えなくなり愛想をつかしてしまったりすることに繋がります。
●どのような関係を築けばいいのか
上下関係がダメだと言うならば、愛犬といったいどのような関係を築けばいいのでしょうか。
私は、あまり理想の関係というものに囚われすぎない方がいいと考えています。
犬はそれぞれ違います。飼い主もそれぞれ違います。飼育環境だって違います。
それだけ違うのですから、理想の関係性の形はそれぞれの家庭によって違うのではないでしょうか。
どのような関係を築けばいいのかと考えるよりも、まずは愛犬の行動ひとつひとつに注目してください。
そして愛犬の望ましい行動はどんどんしてくれるように接していきましょう。
困った行動はそれが問題に発展しないような接し方や工夫をおこないましょう。
動物は行動した直後に何かが起こるとその行動を繰り返すようになったり繰り返さなくなったりします。
そういった行動と環境の関係性には様々な法則があり、行動研究によって明らかにされたそれらの法則を応用しながら愛犬の行動的問題とも向き合っていきます。
学習は、躾やトレーニングの場でだけに生じるものではありません。
日々繰り返される日常の中の行動一つ一つに学習は生じています。
それらと丁寧に向き合っていくその先に愛犬との楽しい暮らしが待っているのではないでしょうか。
さいごに
今回は長年ドッグトレーニングが掲げてきた上下関係について書いてきました。
現在の世界的に見たドッグトレーニングの最前線では、もう上下関係や主従関係という考え方は用いられていません。
今は学習理論や動物福祉に基づいた取り組みが提案されています。
犬が吠える時、噛みつく時、言うことに従わない時、そこには理由があります。
そしてそれは飼い主への挑戦では決してありません。
インターネットやトレーニング本にもまだまだ上下関係の重要性をうたうものがたくさんあります。
多くの飼い主が混乱し悩まれていることと思います。
今回の記事が皆様のモヤモヤを解消する助けになれば幸いです。
参考書籍:
Lars Fält , Hundens språk och flockliv , pisma , 2004
Yrsa Franzen Görnerup , Vardagslydnad (hundens träning och hunägarens vardag) , prisma , 2004
American Veterinary Society of Animal Behavior (AVSAB) : Dominance_Position_Statement