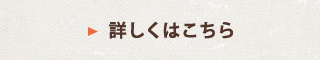犬の心と行動のとらえ方についてちょっと考える
世界で初めて、犬型ロボットと犬の共生の可能性を探る実験が行われました。
とても面白い実験だと思います。
犬がaiboを生き物として認識し共生できるなら、犬たちの暮らしはさらに充実したものになるかもしれません。
夢がありますね。
ただこの実験の評価方法についてちょっと思う事があり、今回取り上げたいと思います。
この実験では、哺乳類動物学者の先生が、犬たちがaiboに対して見せる行動から、その時の犬たちの気持ちを解説されています。
「aiboに対して少し警戒。aiboにお座りなどの指示をするとすぐにやってきて我先にと指示に従った」
→aiboに対し、少し嫉妬している
「aiboを囲い内に入れると活発に遊び始め、初めてaiboにおなかを見せてじゃれていた」
→aiboを仲間とみなし、心を許している
というように、犬たちが見せた行動から、彼らの心理を推測して解説されています。
そしてそれらの推測をもとに、犬はaiboを生き物だと認識しているという結論に至っています。
観察される行動から、心を推測するという方法に反対はありません。
私たちドッグトレーナーも、犬の行動から彼らの気持ちを推測しています。
ただそこで問われるのは、評価の対象となっている行動が、心をとらえるために、どれだけ妥当かということです。
私は、、、
この実験で解説されている犬たちの心理は、哺乳類動物学者の先生個人の主観による想像が大きく影響していると思うのです。
aiboにお座りの指示を出した時、犬がすぐにやってきて指示に従ったという行動は、「aiboに嫉妬している」ととらえるだけの妥当な行動でしょうか。
aiboにおなかを見せてじゃれていたという行動は、「仲間とみなしている」ととらえるだけの妥当な行動でしょうか。
主観的にとらえたものを結論にしてしまうと、評価する人によって結論が変わってしまします。
それでは実験として成立しません。
行動から、目に見えない心をどうやってとらえるか、とても難しい問題です。
心理学でもこの問題は議題として取り上げられるみたいですね。
この記事にも取り上げられています。
「4 方法論的行動主義の問題」p10
一部抜粋します。
新しいことを研究するときには、その新しく扱う心を、どうやって行動からとらえるかが常に問題になって、その人がどれだけArtistoryをもっているかが問われてしまいます。
Artistoryという言葉は、芸術的なセンスや、熟練、熟達したすぐれたアイデアという意味で使われています。
行動から心をとらえるためには、芸術的なセンスのある発想から生み出された研究方法が必要ということです。
ここで紹介されている同調行動の実験(p11)はおもしろいですね。
人が他人に同調する度合いを、長さの単位で評価することができるそうです。
今回のaiboの実験でも、誰が見ても「この犬はaiboを仲間とみなしている」と評価できるような測定方法を見つけることができたら、さらに素晴らしい実験になったかもしれませんね。