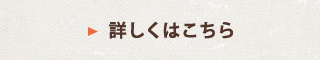愛犬にご褒美を受け取ってもらうために必要な事。
しつけと称して子供たちが虐待される事件が相次ぐ中、来年に施行される改正児童虐待防止法に向けて厚労省から体罰を禁止するための指針案が発表されました。
体罰のガイドラインばかり報道されているので批判がたくさん出ていますが、これを機にではどうすればいいかという所に目を向ける人が増えることを望みます。
褒めるか叱るか?
体罰の線引きは?
このような議論はドッグトレーニングの世界でも長年繰り返されてきました。
現在のドッグトレーニングでは褒めて教える方法が浸透して、多くの飼い主が褒める事に目を向けてくれているように感じます。
今回はその褒めて教える方法を成功させるためのカギとなるご褒美について取り上げます。
ここで取り上げるご褒美とは、ほめ言葉をかけることや撫でることなども含む褒める行為全般を指します。
褒めて教える方法とは、ただ褒めればいいというものではありません。
ご褒美がご褒美として機能するために必要な事をABA(応用行動分析学)の側面から考えていきます。
ABAとは→コンピスについて
ABAではご褒美にあたる刺激を強化子と呼びます。
| <用語解説>
強化子とは、ある行動に随伴して出現することによって、その行動の将来の出現頻度を増加させるような刺激もしくは環境変化のこと。(はじめてまなぶ行動療法より) |
●行動に随伴して出現する
ご褒美(強化子)は行動に随伴して出現する必要があります。この「随伴して」とは、基本的に行動の直後にその場で出現するという意味です。
そして行動の直後には60秒以内という目安があります。この60秒という時間は膨大な行動実験による知見に基づいた時間です。適当なものではありません。
行動の後にご褒美をあげてその行動に変化が見られたとしても、そのご褒美の提示が行動から60秒以上たっているなら、その行動の変化はご褒美ではなく他の刺激の影響を受けて変化した可能性が高いということになります。
また60秒以内であったとしても、行動後のご褒美の出現が遅くなればなるほど、その行動に影響する効果も弱くなります。
そのため行動と同時かもしくは1秒以内にご褒美を提示することが効果的とされています。
●環境の変化
強化子の用語解説にある環境の変化という表現に注目しましょう。
ご褒美(強化子)は行動の直後に存在しているだけではダメで、行動の直前にはなかったものが行動の直後に出現する、もしくは行動の直前にあったものが行動の直後に増大するという環境の変化が必要です。
「行動の直前にあったものが行動の直後に増大するという環境変化」とはどのようなものでしょうか。
例えば、視界にすでにあるモノの数が増える、形が大きくなる、近づいてくるといった出来事もご褒美として機能する可能性があるという事ですね。
●常に同じものがご褒美になるとは限らない
いつも用いているものがご褒美になるとは限りません。
犬のあご元を撫でる行為で考えてみましょう。
犬が飼い主に体を摺り寄せている状況と、犬がオモチャのボールを抱えてかじっている状況では、同じ撫でるという行為でも犬の受け取り方が大きく変わってくる可能性があります。
ボールを抱えてかじっている犬は、あご元をなでる手をボールを奪おうとしている手と感じてしまうかもしれませんね。そのような状況ではその撫でる行為もご褒美にはならないでしょう。
状況によってはご褒美がご褒美ではなくなるという事を覚えておきましょう。
●犬によってご褒美は変わる
ご褒美を選ぶ時、その犬の好みを知っておくことはとても大切です。
例えばオモチャに対して犬の好みは顕著に現れます。
ボールを追いかけることが好きな犬、笛付きのオモチャを噛んで音を出すことが好きな犬、ぬいぐるみのような柔らかいオモチャをしゃぶるように噛むことが好きな犬など、犬によって遊び方や好みは様々です。
食べ物をご褒美として用いる場合でも、味や香などに好みが出てきます。
今用いているものが本当にご褒美として機能しているかどうかを確認しなければいけません。
この確認を怠ればトレーニングは失敗します。
●犬が「褒められた」と受け取らなければ褒めていないのと同じ
飼い主が褒めているつもりでも、愛犬が「褒められた」と受け取っていなければ、それは褒めていないのと同じです。
ではどうすれば褒められたと受け取ったことが分かるのでしょうか。
愛情をこめて褒めているから間違いない?
褒めて犬が喜んでいるから間違いない?
もちろんそれらはとても大切な事です。でもより確実に確認するためには少し不十分です。
もしも行動の変化を期待して褒めているのであれば、冒頭にある強化子の用語解説を思い出してください。
愛犬を褒めて(ご褒美を提示して)、その結果愛犬の行動が増加したのを確認してはじめて犬はその行動に対して「褒められた」と受け取ったと言えるのではないでしょうか。
●受け取る側が正しい
飼い主がどのようなつもりであっても、受け取る側の犬が答えです。
飼い主が愛犬はこれが好きなはずと考えて与えたものでも、それがご褒美として機能するかどうかは分かりません。
たくさん褒めているにもかかわらず、なかなか望む反応が返ってこないことにいら立ちを感じる方もいらっしゃるかもしれません。
でもそこで頭が悪いとか飼い主を見下していると言って、愛犬を責めたところでまったく意味はありません。
犬はその状況の中で正しく行動しているだけだという事を理解してあげてください。
だから伝えたいことを伝えるために何が足らないかを考えましょう。
●飼い主が提供するものだけがご褒美ではない
ご褒美は飼い主から提供されるものだけとは限りません。
トレーニングの場だけではなく、犬は日常の中で常に学習をしています。
例えば、愛犬がゴミ箱を倒すという行動を繰り返すとします。
ゴミ箱を倒した結果、中から食べ物が出てきました。この場合その食べ物がゴミ箱を倒すという行動へのご褒美となります。
ゴミ箱を倒したら食べ物が出てくるという環境がある限り、その犬はゴミ箱を倒すことをやめることはできないでしょう。
このように日常の中で自然な形で出現するご褒美によって繰り返されている問題行動はたくさんあります。問題行動が繰り返される環境があると、そこで褒めて教えていくことが難しくなってしまうかもしれません。
問題行動に影響を与えているご褒美を特定することが、問題を解決するカギになることもあります。
今回はドッグトレーニングや犬のしつけで褒めて教えていくためのカギとなるご褒美について取り上げてきました。
飼い主が褒めているつもりでも犬にそれが伝わっていないということはよくあるんですよね。
褒める時に愛犬の頭をワシャワシャ撫でている光景をよく目にします。
愛犬を抱きしめて左右に振っているような光景も目にしたことがあります。
飼い主のそれらの行為は、はたして犬に伝わるでしょうか。
ちょっと考えたいことですね。
(参考書籍:はじめてまなぶ行動療法、メリットの法則、使える行動分析学、行動分析学事典)
コンピスでは月に1回無料セミナーを開催しております。そちらも宜しくお願い致します。→12月の無料セミナーのお知らせ
↓↓ブログランキングに参加しております。クリックしていただければ励みになります。

ドッグトレーナー・訓練士ランキング
![]()
にほんブログ村