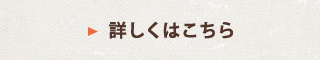多面的なモノの見方 ①
「夜に吠える犬をケージに入れて無視をしたら、朝までずっと吠えていました。」
これは、ドッグトレーナーからアドバイスを受けた飼い主さんに伺った実際にあった出来事です。
そのコはよだれを垂らし目を血走らせてずっと吠えていたそうです。
一晩中、そのような状態で吠え続けていた犬はどれだけ苦しかったでしょう。
吠えずに横になり眠った方が本人にとっても楽だったはずです。
でもそうはせず、目を血走らせてまで吠え続けていた所を見ると、
自分で自分の行動を止める事すらできなくなっていたのではないでしょうか。
このような事が実際にあることから私は、
「問題行動は環境に制御され、犬自身もその行動で苦しんでいる」
という考えを持っています。
今回のテーマは、犬がここまで激しく吠え続ける事の要因に関わることです。
インターネットで目にする情報の中には、「問題行動を治すのは簡単。それは無視をすること」というような内容の記事をよく見かけます。
このような記事の多くは「消去」という行動の原理について書かれています。
専門書によると、消去は以下のように説明されています。
「これまで強化されていた行動に対して、強化の随伴性を中止すると、強化の随伴性を導入する以前の状態まで、その行動は減少する」(行動分析学入門より)
簡単に言うと、
「行動することで今まで得られていた好ましい結果が、行動しても得られなくなる、ということが起こると、その行動は無くなっていく」ということですね。ざっくり言うと!
「要求吠えには無視をしろ」という提案は、吠えても飼い主からの注目が得られないことで吠えなくなっていく、ということを期待して提案されています。
しかし事はそう単純ではありません。
消去が起こる時、必ず一緒に起こる事があります。
「消去バースト」または「バースト」と呼ばれるものです。
消去バーストとは、
「消去手続きを開始した直後、一時的に、行動の頻度や強度が爆発的に増えること」(行動分析学入門より)
というものです。
この消去バーストという出来事を甘く見てはいけません。
「一時的に」と書かれていますが、どれくらいの時間、どれくらいの強度・頻度で行動が増えるかは、
その犬の特性や、その行動が繰り返されてきた期間、またその行動の周りの状況などに大きく左右されます。
そのあたりを考慮せずに単純に消去だけを起こそうとすると、冒頭のような辛い経験を犬にさせてしまうのですね。
単純に消去の学習を起こさせようと乱暴な方法がおこなわれた結果、犬に辛い思いをさせてしまうというのは、行動分析学を学び始めた初学者ドッグトレーナーに多いと思います。
このようなこともあり、この消去バーストを伴う「消去」という学習は、本人に苦痛を与える方法という悪いイメージを持たれ、動物福祉を考慮したトレーニングでは嫌われる傾向があります。
しかし、「消去=悪いもの」と決めつけるのはちょっと早計なのですね。
次回はそのことについて取り上げます。