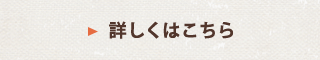犬のリードを引っ張る理由とその向き合い方を考える。
お散歩で犬がリードを引っ張るのは、前方に興味の惹かれるものがあったり、引っ張った結果そこにたどり着けたという経験による学習があったり、その他にリードが後ろに張ることで体が前方に動くという行動的性質や犬種特性など、様々な要因が考えられるのですが「リーダー願望の現れ」ではありません。
— コンピス (@kompismedhund) July 12, 2025
先日投稿したこのポストにある犬がリードを引っ張る要因について少し詳しく書いていきます。
■興味を惹かれてリードを引っ張る
散歩中に犬がリードを引っ張る行動にはさまざまな理由があります。
その中でも一番イメージしやすいのは「興味にひかれて引っ張る」ということでしょう。
犬は好奇心旺盛な動物です。
そして外の世界は新しいニオイや音、動くものにあふれています。
特に嗅覚に優れる犬にとって、屋外のニオイには単なる臭いではなく、そこにどんな動物がいたか、いつ通ったかといった膨大な情報を得ることができるでしょう。
「犬は嗅覚で世界を見る」と表現されているのを目にしたことがありますが、とてもうまい表現だと感心しましたね。
犬にとって散歩中に嗅ぐニオイ一つ一つは私たちでいうニュースやSNSみたいなものなのかもしれません。
愛犬がニオイに夢中になるあまりリードをグイグイ引っ張って大変な場合は、歩道の端から少し離れた位置を歩いたり、ゴミ捨て場や食べ物がよく落ちているベンチなどニオイの強い場所は避けて歩いたりするのもいいかもしれません。
■学習に影響を受けるリードの引っ張り
散歩中に犬がリードを引っ張るのは、学習による影響も大きいといえます。
その一つに「正の強化」という学習があります。
これは、ある行動の直後に犬にとって望ましい状況が出現すると、その行動が繰り返されやすくなるというものです。
たとえば、
散歩中、犬が電柱を見つける
↓
引っ張って近づく
↓
電柱にたどり着ける(電柱のニオイを嗅げる)
このような体験が繰り返されることで犬は電柱を見たときにより強く引っ張って電柱まで歩いていくようになっていくでしょう。
これに対してよく提案される対応方法のひとつに「犬が引っ張ったら立ち止まる」という取り組みがあります。
これは「引っ張っても前に進めなければ、その行動はなくなる」という考え方に基づいています。
しかし、実際に試すとなかなか難しいことが分かります。
多くの場合はこうなります。
犬が引っ張る
↓
飼い主が止まる
↓
犬も止まる
↓
飼い主が再び歩き出すと、犬はダッシュでまた引っ張る
なぜこうなるのでしょう?
少し細かく見てみるとイメージしやすいです。
飼い主が止まっている間、犬は動けず、状況は変わりません。この間は犬のリードを引っ張る行動は減るでしょう。
でも、飼い主が歩き始めた瞬間、状況に変化が起きます。
たとえば、足が動かせるようになったという感覚、目標に少し近づけたことによる視覚的な変化。
これらが「報酬」として働き、その都度に引っ張る行動を強化してしまう可能性があるのですね。
学習理論的に考えると、別の望ましい行動を強化することで結果的にリードの引っ張りが減少するような取り組みができるかもしれません。
たとえば、「飼い主のあとをついてくる」や「歩きながら飼い主の顔を見る」などの行動を強化できれば、結果的にリードを引っ張る行動の減少が期待できるかもしれませんね。
リードを引っ張る行動に影響する学習は他にも考えられます。
お散歩がニガテで屋外にあるさまざまな刺激を怖がる犬は少なくありません。
こうした犬たちも強くリードを引きながら歩くことがあります。
この引っ張る行動の目的は「逃避」です。
恐怖を感じるものから距離を取ろうとして犬はリードを引っ張るのですね。
これを「負の強化」という学習に沿って考えると分かりやすいです。
負の強化とは、行動の直後に不快な状況が消失することで、その行動がより起こりやすくなる現象をいいます。
屋外は、犬にとってたくさんの刺激にあふれています。
道路を走る車、歩道を行き交う人や自転車、工事現場の騒音、突然飛び立つ鳥、そして体に触れる風まで、刺激の種類は多様です。
たとえば、犬が車を怖がり、その場から離れようとしてリードを引っ張るとします。
車から距離を取れたことで不安が軽減されるでしょう。
しかし、その先でまた別の車や通行人と遭遇する――この繰り返しによって、お散歩が「逃げ続ける」というかたちになってしまうのですね。
このようなタイプの行動にはどのように向き合えばいいのでしょうか。
「逃げようとしても逃げられなければ、そのうち逃げる行動は減っていく」と考える人もいますし、「怖いものから逃げるから、いつまでも慣れないんだ」という熱血指導の姿勢で向き合おうとする人もいます。
でも、どうでしょうね。
うまくいくこともあれば、うまくいかないときもあります。
ただ、うまくいったときの印象が強いため、うまくいかなかったときのケースにあまり目が向けられていないように思います。
いわゆる生存者バイアスというのでしょうか。
精神論に基づく熱血指導がそれほど効果があるとは私は考えていません。
行動はそんなに単純なものではないでしょう。
刺激に対する感受性は犬によって違います。
そして屋外は状況が目まぐるしく変わります。
そこで「慣れ」が生じるだけの条件を揃えることは簡単ではありません。
強引に進めようとすれば、多くの場合その取り組みは失敗してしまします。
またうまくいかなかったときはとても深刻な状況になる可能性も考えないといけません。
犬がさらに怖がるようになったり、散歩自体を拒絶して攻撃的な行動を示したりすることもあります。
だから、私はこうした一か八かの方法はおすすめしません。
屋外が怖くてお散歩が苦手な犬には、まず安心して歩ける道を1本作りましょう。
静かな時間帯や、人や車が少ない道を選ぶのがおすすめです。
日ごとに道を変えない方がいいでしょう。
毎回違った刺激に直面しているとなかなか「慣れ」は生じないからです。
飼い主が1人より2人、3人と一緒に歩く方が犬は歩きやすくなります。
大好きなおやつを持っていき、適切なタイミングであげるのもいいですね。
「怖いことは起こらない」「むしろ楽しいことがある」という体験の繰り返しで少しずつお散歩できるようになるでしょう。
■動物としての行動的性質
散歩中に犬がリードをグイグイ引っ張る理由について、動物としての行動的性質からも考えてみます。
リードがピンと張ったとき、犬の体には後方に引っ張られるような感覚が生じます。このとき、犬はその力に反発して前に進もうとする反応を示します。刺激に対して一定方向に動こうとするのは多くの動物が持っている性質で、生物学ではこれを「走性」と呼びます。
ドッグトレーニングの世界では、この性質を「抵抗反射」と呼ぶこともあります。
つまり、引かれると反対方向に動こうとする体の仕組みが働いているのですね。
このため、リードが張れば張るほど犬はより強く前へ進もうとし、結果的に引っ張りがエスカレートしてしまいます。
では、この引っ張りを防ぐにはどうすればよいのでしょうか。
リードをたるませておくことが大切とよく言われますよね。
その通りです。
しかし、これを実現するためには、リードの張り具合や歩くスピードを細かく調整する技術的な工夫が必要になります。
犬は人より歩くスピードが速いため、単純にたるませることだけを意識すると、飼い主も犬に合わせて走るような散歩になってしまい、現実的にはとても大変になってしまいます。
他の方法として、長めのリードを使うことも有効です。
一般的なリードは100cm〜120cmですが、これを150cm〜180cmほどの長めのものに変えるだけで、犬の歩き方が変わることがあります。
リードが長くなることでピンと張りにくくなり、犬に「引っ張られている」という感覚が生じにくくなるため、抵抗反射が起こりにくくなるのです。
※一般的にフレキシブルリードが好んで使われるのはこれが理由でもあるのですが、フレキシブルリードは様々な危険があるため私はおすすめしていません。
長いリードを使う場合には注意も必要です。
絡まりやすくなるため、狭い道や人が多い場所では扱いに気を付けなければいけません。
また、犬との距離が広がることで制御が難しくなるため、周囲への配慮も欠かせません。
安全のため、人や車が多い場所ではリードを束ねて短く持つなどの工夫が必要です。
これら以外にも、散歩中に吠える行動に伴うリードの引っ張りや、犬種によって引っ張りやすくなる例などもありますが、少し長くなり書ききれないので今回はこのあたりで締めませていただきます。
愛犬のリードの引っ張りは大変ですね。
毎日の散歩で腕や手首に負担がかかり、腱鞘炎になってしまう飼い主さんもいます。
でも、その裏には必ず理由があります。
犬の好奇心や不安、学習の積み重ねなど、さまざまな要因が影響しているわけです。
その理由を考えて、少しずつ工夫を重ねることで、お散歩はもっと楽しくもっと快適な時間に変わっていくでしょう。
愛犬との楽しいお散歩ライフをぜひ一緒に見つけていきましょう。