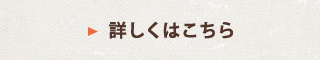精神論が問題解決を妨げる
精神論
事実や数字に基づいた客観的、論理的な考え方ではなく、精神と物質の関係に対する主観に依存する物事の考え方。
(日本語表現辞典Weblioより)
「厳しい経験が人を強くする」
「強い心を持っていないといざという時に力を発揮できない」
世の中は精神論であふれています。
スポーツやビジネスの世界でもこのように考える方は多いでしょう。
私もこのような事を少しも考えないと言えばウソになります。
ただこの精神論で物事を考えることの危険性は理解しておくべきだと私は考えています。
例えば
中学校や高校の部活動で、水分補給が禁止されていた時代がありました。
脱水を起こして立てなくなっているのに、立てなくなったのは気合が足りないからだとされていました。
今考えると誰もが“アタマガワルイ”と分かるでしょう。
しかし当時はそれが当たり前でした。
立つことができないという事の原因は、気合が足りない事だと考えるのなら、
そこで必要なものは何でしょうか?
気合を入れること?
猪木のビンタですか?
死んでしまいます。
このような事は冗談でもなんでもなく、実際に行われてきたということがとても恐ろしいことなのです。
行動の原因を精神論から考えることの危険性はここにあります。
目の前で起こっている問題に対して適切な対応がされず、頓珍漢なことがおこなわれてしまいます。
犬のしつけの世界で見てみましょう。
私たちは精神論で物事を考えがちです。
それは犬たちに対してもおこなわれ、彼らへの接し方も決定づけられます。
何か愛犬が好ましくない行動をして、その問題を何とかしないといけない時、
多くの人が叱ることをまず考えるのではないでしょうか。
私たちはつい犬たちを人間のように考えてしまい、ここで人間が思う精神論を当てはめようとしてしまいます。
愛犬が好ましくない行動をするのは愛情、信頼関係、威厳、尊敬の念といった精神的なものが足りていないから、それらが伝われば愛犬は飼い主の事を理解してくれるはず、、というように。
「褒めるだけではダメ、時には厳しく叱らないと」
「褒める事と叱る事、その両立が大切」
といった考え方は精神論の典型的な例だと思います。
このような精神論に基づく考え方は、動物を脅かし痛めつけるとどうなるかといったとても大切な考え方よりも優先されてしまいます。
問題解決よりも、叱ること自体が目的になっているようにも感じます。
重要な事は、その問題が繰り返されないこと、または悪化しないことではないでしょうか。
褒めることが良い、叱ることはダメ、と言いたいのではけっしてありません。
問題に対して適切な対応がされているかどうかを考えていただきたいのです。
問題を目の前にするとき、精神論が解決の妨げになると私は考えています。