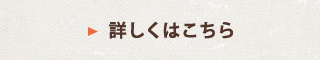愛犬の問題行動。もともとそういう性格だから?仕方がない??
吠える、噛みつくといった愛犬の問題行動と向き合う時、多くの方が「どうしてそんなことをするのだろう」と疑問を持たれると思います。
愛犬が飼い主に噛みつくのは、支配性が強いからでしょうか。
愛犬が他犬に吠えるのは、怖がりな性格だからでしょうか。
従来のドッグトレーニングでは、その犬の「性質」や「性格」が問題行動の原因になっていると考えられ、その好ましくない原因を正そうとトレーニングがおこなわれてきました。
しかしトレーニングをしてもなかなか問題が改善されないことを、「もともとそういう性格だから」と半ばあきらめてしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そういう性格だから?
それは本当に仕方のない事なのでしょうか?
今回、犬の問題行動のトレーニングに深く関わる「行動修正」について書かれた論文を取り上げたいと思います。
この論文の中で、行動修正で用いられる特徴的な行動観(行動に対する考え方)が分かりやすく取り上げられていました。
犬の問題行動と向き合うドッグトレーナーにとっては、とても大切な内容だと思います。
飼い主さんには、このような考え方がありますよ、という紹介もかねて書いていきます。
行動に対する考え方の一つに、「人間は行動存在の場である」という考え方があります。
この言葉だけを聞くとなんとも冷たい感じがしますね。
人間には心や気持ちは無く「行動」だけで構成されていると受け取れるような。。
この考え方を犬に当てはめるなら、犬は行動存在の場である、となります。
この言葉を見ただけで、読む気が失せてしまうドッグトレーナーさんが出ないかと心配になってしまいます。
「人間は行動存在の場である」とは、
人間という「場」にどのような行動が存在しているかによって、その人がどのような人間かが決定されるという考え方です。
この考え方では、
「悪い子供は存在しない。悪い行動を持った子供が存在するだけである。」
「悪い行動を消去して、良い行動を形成すれば、良い行動を持った子供が存在するのである」
と紹介されています。
悪い子供とは、「叩く」「悪口を言う」「いじめる」といった“悪い行動”を持った子供を、「悪い子供」という名前でそう分類しているだけという事です。
だから、叩く、悪口を言う、いじめるといった“悪い行動”をなくし、
言葉で伝える、褒める、一緒に遊ぶといった“良い行動”を形成すれば、
良い行動を持った子供が存在することになります。
このように個人の「良い・悪い」などの性質や、性格、才能といったモノは、行動を観察することで付けられた名前、分類だとします。
だから行動が変わることで、その行動から連想された性質や性格と呼ばれるモノも変わっていくことになると考えられます。
注目するべきは、性格や性質といった精神的なモノではなく行動であるということです。
行動に注目するという意味で、「人間は行動存在の場である」という表現が用いられているのですね。
ちょっと犬に置き換えて考えてみましょう。
「甘やかされた犬」がいるとします。
これを同じように考えると、
吠える(要求する)、呼んでも来ない、噛みつく(不快な事をすると)etcといった行動を持った犬が、“甘やかされた犬”という名前で分類されます。
吠える、呼んでも来ない、噛みつくという行動を見て、その様子から“甘やかされた犬”と呼んでいるということです。
こう考えると、吠えない、呼んだら来る、噛みつかないと行動が変わることで、「甘やかされた犬」は「甘やかされていない犬」になります。
注目されるべきは“甘やかされた精神”ではなく行動ということです。
「支配性の高い犬」「神経質な性格の犬」といった表現も、同じように行動によって分類された名前だと考えます。
では、どうしてこのような変わった考え方をするのでしょうか。
それを説明するのに、論文には伝統的な2つの行動観が取り上げられています。
※ここで取り上げている「環境随伴性説」と「生物学的限界説」という言葉は、行動修正の場において、それぞれの考え方を区別するために、この論文の中だけで用いられている言葉です。
1つ目の行動観は、
行動にはそれぞれ目的があり、行動はその目的達成を必要とする環境(状況)によって制御されている、というものです。
この考え方では、環境を操作することで行動は変わる。
上記に紹介した通り、性質、性格、才能といった構造を行動に持たせることで、
それらも修正可能である。と考えます。
この考え方をこの論文では「環境随伴性説」と呼んでいます。
分かりやすくするために例を出します。
ごはんの前に吠える犬がいるとします。
吠える行動の目的はごはんをもらう事です。「袋の空いた音」が聞こえた時に、吠えたら、「ごはん」がもらえた、という状況(環境)によって吠える行動は制御されています。
袋の開く音が聞こえなければ吠えません。
吠えても「ごはん」が出てこなければ、目的は達成されないため、吠えなくなっていく可能性があります。
この「吠える」という行動を見て“わがままな性格”と判断しているのなら、吠える行動が変わることで、“わがままな性格”も変わると言えると思います。
注目すべきは、性格や性質ではなく、行動と環境の方であるということです。
現在、ドッグトレーニングの世界で注目されているABA(応用行動分析学)もこの行動観に基づいています。
2つ目の行動観は、
性質、性格、才能といったのものは、生物学的、解剖学的、遺伝的に決定されるという考え方です。
性格や性質といったモノは、犬種や性別、遺伝などによって決まるということですね。
こちらの方が一般的な考え方だと思います。
ただ性格や性質というものが遺伝などで決まるのならば、行動修正(トレーニング)によってそれらに影響を与えるのには限界があると考えられます。
論文ではこの行動観を「生物学的限界説」と呼んでいます。
「環境随伴性説」と「生物学的限界説」これら2つの行動観については、どちらが正しいか、どちらが真実に近いかを論じるのではなく、これら2つの立場を明確に区別することが大切だと書かれています。
そしてどちらの考え方をとるかは、問題行動と向き合った時の「戦略的な立場の選択」になるとされています。
例えば生物学的限界説のような立場では、
獣医師が、問題行動の原因として、その犬の性質(攻撃性、過敏性、恐怖性)に注目し、精神活動に影響を与えるお薬を処方する事もあると思います。
ブリーダーが、問題行動の原因として、その犬の性格に遺伝的要素が強く影響していると考えるならば、選択交配という方法によってその問題行動と向き合うかもしれません。
問題行動と向き合った時の立場によって、おこなう方法は変わるという事ですね。
ではトレーニングという実践の場において、どちらの考え方が有用でしょうか。
それを考えるためには、この2つの立場がどのような行動傾向を生むかを考える必要があります。
「環境随伴性説」では、行動修正の失敗はあくまでトレーニングプログラムの整備の失敗と考えます。
対象者の意識、性格、やる気といったものは行動が持っている構造の一部だと考え、環境が変われば行動も変わると考えられるからです。
この場合の行動修正の失敗は、そのプログラムの構造に責任があるということになります。
トレーニングプログラムの構造に徹底した責任を持つという事は、行動修正の失敗に対して、プログラムに何が欠けていたのかを考える機会を作ることができ、行動修正を促進させるきっかけとなります。
環境随伴性説の立場をとることは、常に行動修正の実践を可能にしつづけることができるということです。
トレーニングにおいて、この考え方はとても有用な考え方と言えます。
一方で、「生物学的限界説」の立場からすると、トレーニングの失敗は、自身の説の正当性を強めることになります。
トレーニングという実践の場において、生物学的限界説の立場に立つことは、「行動修正は必ずしも成功しなくてもよい」という主張を作り出してしまう事にもつながります。
場合によっては、生物学的限界説は行動修正の失敗に対する説明(言い訳)として表れることがあり、本来の本質とは別の所で用いられることがあると指摘されています。
従来の問題行動に対するドッグトレーニングは、犬の性質や性格に原因があるとされ、主に生物学的限界説の考え方に基づいておこなわれてきました。
そして、それら原因と考えるモノに対して、トレーニングによって影響を与える事には限界があることも前提とされ、多くの人がその部分を割り切ってトレーニングをおこなってきたように感じます。
かくいう私も、トレーニングの失敗に対して「そういう性格だから」と割り切っていた過去があることを否定できません。
それを「全ての犬を救えるわけではない」という言葉で納得させていたのだと思います。
環境随伴性説のように、行動に注目するということで、
対象者の性格や気質のせいにすることなく、問題行動と向き合うことができるようになります。
この考え方はあまり一般的ではないかもしれませんが、心理学の世界で用いられている伝統的な行動観のひとつです。
問題行動に対するドッグトレーニングの発展にはなくてはならないものだと私は考えています。
多くのドッグトレーナーがこの考え方に触れ、適切なトレーニングが、必要としている人たちのもとに届いてくれたらいいなと思っています。